近年、IT技術やSNSの普及により、インターネットを利用したサービスが爆発的なヒットを記録する事例が増えています。
これらの成功の背景には、「グロースハック」と呼ばれるマーケティング手法の活用がある場合が多く、「グロースハック」という言葉をよく耳にするようになった人も多いかもしれません。
技術革新の影響でビッグデータを活用した事業活動を展開する企業が増え、時代の流れやニーズの移り変わりが早い現代において、変化に対応できる事業運営が不可欠となっています。
このような背景から、グロースハックが注目を集めています。
本記事では、グロースハックの意味、必要性、従来型のマーケティングとの違い、具体的な手順、そして成功させるためのポイントについて、ソースの情報に基づいて包括的に解説します。
グロースハックとは?
グロースハック(Growth Hack)は、2010年にアメリカQualaroo社CEOのショーン・エリス氏によって提唱されたマーケティングの概念であり、新しい職種として生まれた言葉だとも言われています。
Growthは「成長」を、Hackは「テクニック」や「方法」、あるいは「(プログラム作成などで)仕組み化する」「プログラムに取り込む」といった意味を持ちます。
ショーン・エリス氏はポジティブで広義なニュアンスとしてHackという言葉を使用し、「成長を推進し続ける」「成長を維持し続ける」といった理念的な意味合いも含まれているとされています。

ウェブマーケティングとしてのグロースハックは、まずサービスや製品に関するさまざまなデータやユーザーの声などを収集・解析し、成長を妨げる要因を見つけ、改善のための仮説・施策を立案・実施します。
その結果を検証してフィードバックをかけ、さらにより効果のある改善を実施し繰り返すことで、サービスや製品の品質や使い勝手の向上・進化に取り組み、サービスや製品を成長させていくマーケティング手法です。
これは、プロダクトの持続的成長を行うための手段・戦術がプロダクト自体に組み込まれている状態とも言えます。
グロースハックは「プロダクト成長のための継続的な検証・改善」を意味し、「プロダクトを成長させるため、継続的に検証・改善を続ける」ことを指す考え方です。
サービスやプロダクトを成長させるために、さまざまな改善施策を同時的に行い、その都度効果測定をするため、成長スピードが非常に速いことがグロースハックの特徴です。
これは、マーケティングとエンジニアリングの両輪からプロダクトが売れるように設計し、厳しい状況下でもビジネスの成長を促せる考え方と言えます。
なぜグロースハックが必要なのか?
FacebookやTwitterなどのWebサービスは、グロースハックで急成長を遂げたと言われています。
数々のヒットサービスを誕生させるグロースハックは、今後のビジネスにおいて必要不可欠だと言えるでしょう。

IT技術やAIが目まぐるしく進歩する現代においては、サービスのライフサイクルが著しく短くなってきています。
これまでのマーケティングのように、緻密に戦略を立てて、多額の予算を投じていると、サービス投入後まもなくして、市場がガラッと変わってしまうこともあります。
また、価値観の多様化、技術革新の変化のスピードが速くなり、さまざまな業界でサービスや製品のライフサイクルはますます短くなっています。
競争相手も同業者のみでなく異業種からの参入もあったりと競争はより激化しており、変化するユーザーにサービスや製品を対応させ、競合企業に対する競争優位性を常にスピードを持って対応し維持していかないと、ユーザーの支持を失い競争に負けてしまいます。
グロースハックは、一つのサービスをできるだけ短期間で拡大し、少しでも長く顧客に利用してもらうための手法であり、このようなサービスのライフサイクルが短い現代においては、間違いなくグロースハックが必要です。
また、大量の広告費やマーケティング費用をかけずに、高い効果を期待できる手法なので、多くの企業が導入するようになりました。
従来のマーケティングとの違い
グロースハックは従来のマーケティングといくつかの違いがあります。
違い1
プロセス全体の改善
従来のマーケティングは商品やサービスの「売り方」を研究、改善する手法であり、商品やサービス自体の開発や研究は別に考えていました。
グロースハックは、商品やサービスづくりの段階から市場ニーズを考え、販売後も常にモニタリングをしながら改善を続ける手法です。
これは、サービス・製品開発とマーケティングの垣根を超え、組織横断でプロセス全体を改善するための考え方なのです。
違い2
低予算で実現
また、グロースハックは従来のマーケティング手法と比較して、大きな予算をかけずに行なうパターンが多いことも特徴です。
予算をかけないためにもデータやアクセスの解析をすばやく行い、PDCAを早く回しながら効果を最大限にするという考え方が必要です。
違い3
グロースマーケティングとの関係性
グロースハックと似た言葉に「グロースマーケティング」がありますが、グロースマーケティングは、製品やサービス、事業、企業の持続的な成長のために、顧客との関係性を強化するマーケティング戦略のことです。
グロースハックは、グロースマーケティングを展開するための手法のひとつとして活用でき、グロースマーケティングはグロースハックを実践していくための戦略であり、両方を組み合わせることが大切とされています。
グロースハックのメリットと役割
グロースハックを導入することにより、いくつかのメリットが得られます。
メリット1
低コストで事業を成長させられる可能性がある

自社のサービスを低コストで効果的に拡散できる手法を取り入れます。
Dropboxが招待インセンティブによってユーザー数を増やした事例や、日本のファッションアプリ「iQON」が広告費用を一切かけずにユーザー獲得に成功した事例などが挙げられます。
コストを抑えながら認知拡大やユーザー増を実現できます。
メリット2
ニーズに合った製品やサービスを開発できる

ユーザーニーズを開発段階から取り入れるため、消費者が望む質の高い製品・サービスを提供できます。
リリース後も継続的にデータを収集することで、スピーディな改善や対策が可能となります。
データをベースに改善策を立案するために効果を上げやすい: ユーザー行動をデータとして可視化し、データを判断基準に改善のための仮説を立てるので、成功確率の高いマーケティングを展開できます。勘や経験、属人化を排除できます。
メリット3
収益力を高めることができる

AARRRモデルというフレームワークを活用して、製品やサービスの成長度合を5つのフェーズに分け、各段階で課題発見・改善を繰り返しながら最適化を図るため、必然的にコンバージョンが高まり、結果安定した収益につながるようになります。
メリット4
利用者を増やし、より多くのユーザーに使ってもらえるようにできる

グロースハックは、広告、口コミなどメディア戦略のみではなく、利用頻度を多くし、広くユーザーに知らしめ、そして顧客満足度をあげて長期間にわたって使い続けてもらえるような仕組みを同時に考えます。
グロースハックの手順
グロースハックを行う手順をご紹介しましょう。
- ターゲットと目標設定/KGI設定/データ基盤構築
- 従来のマーケティング手法と同様にターゲットと目標を設定します。グロースハックでは部門ごとに分けられたKPIを追うのではなく、全社で連動した取り組みが重要であるため、最終目標となるKGIを設定し、それに沿ったデータ基盤の構築を行います。ユーザーニーズの分析にデータをなるべく多く活用し、経験や勘に頼らずデータに基づく設定を行ないます。

- サービスや商品を作る
- 設定したターゲットを狙ったサービスや商品を製作します。グロースハックではサービスをリリース後も常に改善を続けていくので、まずはサービスをなるべく早く市場に投入することを意識しましょう。リリース直後、明らかにユーザーニーズとずれている場合は、サービス自体を見直すことも重要です。グロースハックにおいては、完璧な製品を提供するよりもその都度ニーズを満たすために改善を施すことが大切です。

- サービスや商品の分析と現状把握
- サービスを市場に投入した後は、分析と現状把握を行います。リリース後の分析と現状把握はグロースハックの肝とも呼べる工程です。Webサービスの場合は、ページのアクセス解析などで顧客の動向や好みを確認します。現状を正確にあらゆる角度から把握するために、ユーザーのデータや声をあらゆる角度から収集して分析します。アクセス解析は、ユーザーの属性やサイト内での行動を把握でき、離脱が多い箇所の特定などに欠かせません。ファネル分析は、ユーザーの利用プロセスを段階分けし、大きく離脱されている箇所を把握するために用いられ、改善すべき優先度の高いステップを明確にできます。コホート分析は、ユーザーを一定の条件または属性によってグループ分けし、グループごとに時間経過による行動の変化を分析する手法で、現状把握や継続利用のための施策に役立ちます。

- 改善策の立案/仮説を立てる
- サービスの分析と現状把握から課題が見つかれば、すぐに改善策を検討します。データやアクセス解析を根拠として、サービスの軌道修正を行なうためのプランを立案します。STEP2で把握した情報から「どのような施策が有効か」の仮説を立てます。仮説の精度をあげるためには、データの分析を進めるときに多方面から、さまざまな結果を想定することが重要です。柔軟な発想でアイデアを出せるスキルも必要です。仮説を立てたら、施策のアイデアを幅広く出しましょう。

- 改善策の実行/実践する
- 改善策の立案に社内で合意ができれば、すぐに実行に移します。サービスのライフサイクルが短くなっている現代では、改善策をすばやく実行に移すことができるスピードが勝負を分けます。グロースハックの特徴は、改善策実行までのスピードが早いことが挙げられます。前STEPで立てた仮説を実践すべく、キャンペーンや新しいコンテンツをプロダクトに実装します。施策の実行と評価の段階で重要なのは、まずコストやリソースをかけずに小規模な施策を実行し検証することです。
- 評価と見直し/検証し改善を続ける
- 改善策の実行後は、どのような結果になったのか評価を行なうことが重要です。実践結果から得られた内容について、評価や改善を試みます。実際のデータを参考にしながら、どのような改善案が考えられそうか繰り返し見直すことが重要です。仮に設定した目標に届いていない場合は、再度改善策の見直しを実施して、市場投入します。改善策の評価と見直しを目標達成まで行うことによって、より良いサービスとなっていくのです。ステップ5~6の仮説・検証・改善を、設定したKPIに到達するまで繰り返し回します。目標をクリアしたら次に優先度の高い課題の改善に取り組みましょう。

このように販促手法だけでなく、サービスや商品の改善も含めて行って初めてグロースハックと言えます。また環境変化が早い現代に合わせ、サイクルを高速で回すことが重要です。
グロースハックを成功させるポイント
グロースハックはサービスを急成長させる効果的な手法ですが、闇雲に実践するだけでは、成功できません。
ポイント1
AARRRを理解する
グロースハックを成功させるには、AARRRを正しく理解する必要があります。AARRR(アー)モデルとは、製品やサービスの成長を、「Acquisition(獲得)」→「Activation(活性化)」→「Retention(維持・継続)」→「Referral(紹介)」→「Revenue(収益化)」という5つのステップで分類したときの、それぞれの頭文字を取った言葉です。グロースハックを実践するときは、5つのステップごとに指標を設けて施策を実施し、客観的で合理的なグロースハックを行うことが可能になります。各フェーズごとに、目標や目的を定め、分析をして部分改善を行っていくことで、最終的に製品・サービスの全体的な改善が実現します。
ポイント2
データに基づき分析と検証を行う
グロースハックは仮説を立てて、失敗を繰り返しながらも改善を続ける方法です。仮説を立てる際に重要なのが属人的な経験や勘に頼らないということでしょう。データとデジタル技術を駆使したDXにより、データドリブンな分析と検証を行うことが、グロースハックを成功に導きます。適切にデータ分析して仮説の精度をあげることも重要です。
ポイント3
スピードを意識する
グロースハックでは、PDCAサイクルを短いスパンで継続的に行うことで、再現性のある方法を見つけていきます。全ての施策で成功する必要はなく、改善を繰り返すことで成功の確度を上げていくことを意識しましょう。
ユーザーニーズに合うプロダクトにする: プロダクトやビジネスの成長には、そもそもプロダクトがユーザーに受け入れられるものでなければなりません。AARRRモデルのどのフェーズにおいても、「ユーザーが利用したいプロダクト」であることが大前提です。ユーザーニーズに合うプロダクトにすることが、グロースハックの第一歩ともいえるので、そのためのリサーチやUI/UXデザインをしっかりと行うことが重要です。
ポイント4
専門チームを編成する
グロースハックは、ウォーターフォール型のような従来の開発手法とは異なる手順を踏むため、グロースハックの専門チームを編成することが成功のカギを握ります。グロースハッカーは日本においてはまだ少ないため、マーケターやデザイナーなどグロースハックを構成する要素における専門家を集めてチームを作るとよいでしょう。グロースハッカーには、沈着冷静な分析能力、強い探究心と好奇心、柔軟な思考力と創造力と挑戦する心、ユーザーと同じ視線と同じ感覚になれること、やり遂げる責任感と忍耐力、コストをかけずに施策を行うための工夫する力、機能をあえて捨てる勇気などの資質が求められます。また、企業組織にもグロースハックを推奨する文化や仕組みが求められ、失敗を許容し、失敗から学ぶ企業文化や、各部署を横断しデータを用いて施策を実行していくための適切な権限の付与が必要です。
ポイント5
費用を最小限に抑える
どれだけプロダクトの利用ユーザーが増えて売上が伸びても、莫大な費用をかけてしまっては十分な利益が得られません。データ分析や施策は、コストとのバランスも考えて検討・実施するようにしましょう。
ポイント6
仮説の精度をアップさせる
データの収集とその分析に大きく依存しますが、そこから導き出される改善のための仮説が間違っていたり甘かったりすると、間違えた方向に進んでしまうことがあります。データから見えてくる課題をあらゆる角度から検討し、求める成果を得るための仮説を立案しなければなりません。
ポイント7
グロースハックは考え方が重要である
グロースハックをツールとして単純に実施しても成功できるものではありません。サービスや製品を改善するためにどのように考えるか、ということを順序立てて考えるための思考プロセスです。
グロースハックの具体例
実際にグロースハックで成長を遂げたサービスの具体例を確認することで、自社のサービスをグロースハックする手がかりが掴めるかもしれません。

リリース初期の煩雑なホーム画面を簡易化することでユーザー数が増加しました。さらに、活発なユーザーが登録初日に5人以上の人をフォローしているデータから、「おすすめユーザーの表示」を導入し、ユーザーの定着率が向上しました。これはAARRRの考え方に沿って実施されています。新規登録時のおすすめアカウント表示などで、ユーザーのフォロー数を増やす対策を行いました。
Airbnb

スタートアップ期にホストとゲストをバランスよく集める課題に対し、ホストがAirbnbから「Craigslist」へ宿泊情報を投稿・転載できるボタンを設置しました。Craigslistという無料の巨大掲示板を活用することで、ゲストとホストの両方をバランスよく獲得できた好事例です。Airbnbに投稿すると、地域のコミュニティサイトにも自動的に投稿される仕組みを実装して、ユーザー数を大幅に増やしています。
Dropbox

マス広告にほとんどお金をかけずに利用者を急増させました。新規ユーザーの紹介インセンティブとして無料データ容量を提供し、ユーザー自身が新規ユーザーを呼び込む仕組みを作ることで、広告を使わずにサービスを成長させました。友人を紹介してその人がユーザーになると、紹介者と友人の双方に追加容量をプレゼントする施策を行い、登録数を飛躍的に伸ばしました。ユーザーのデータ分析から、新規ユーザーの三分の一が既存ユーザーの紹介を受けていることに注目し、紹介インセンティブを導入した結果、60%の新規登録者を獲得し、10万人だったユーザー数を1年強で400万人まで伸ばしました。
ガリバー

中古車販売のガリバーは、ホームページを閲覧するユーザーを分析し、3つのパターンに分け、それぞれに適したボタンを設置しました。ユーザーに適した誘導をすることでコンバージョン率のアップに成功しました。

FacebookやTwitterなどのSNSサービスに同時に写真を簡単に投稿できるようにしてユーザーへの価値を高めました。これにより、面白い写真が多くのSNSに拡散され、無料のプロモーションとなり、利用者の増加につながりました。

無料版と有料版を用意し、有料版で無料版にはないサービスを提供することで収益増につなげています。
YouTube

埋め込みコードを提供することで、ユーザーが自分のサイトで動画を簡単に共有できるようにしました。
オンラインゲーム会社 (Uproar)
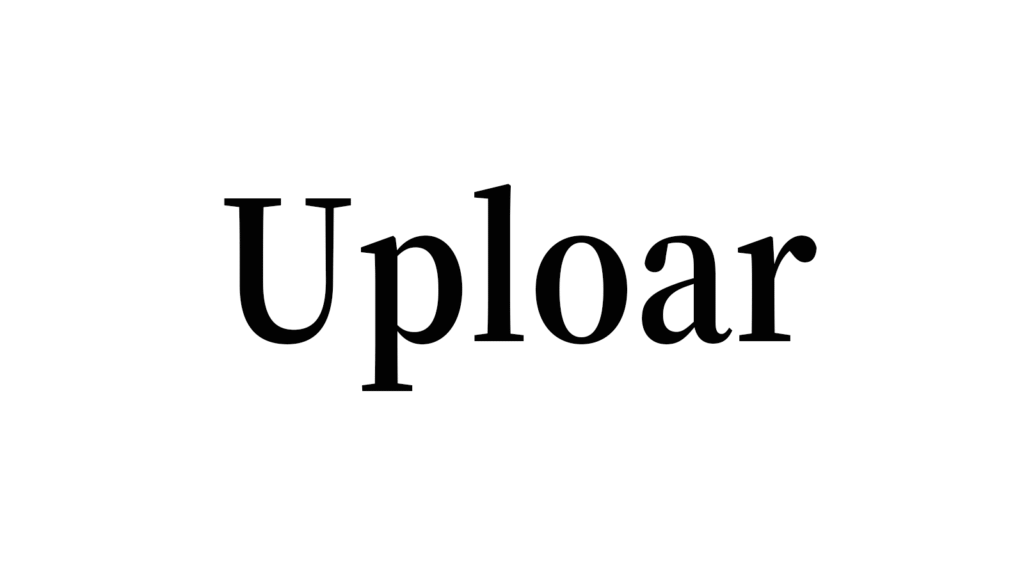
サイト運営者に無料で遊べるゲームを提供し、獲得顧客一人につき50セントを支払うプロモーションを企画しました。これにより、数万のサイトに掲載され、爆発的な顧客増加を生み出し、業界TOPに押し上げまし
これらの事例からわかるように、グロースハックの仕組み自体は単純なことでも、自社のサービスや製品に適合する方法を見つけることが重要です。
エル・タジェールがグロースハックを加速します。
現代はIT技術やAIの進化により、サービスのライフサイクルが著しく短くなっています。このような変化の速い時代において、サービスを継続的に成長させていくためには、勘や経験に頼らず、データに基づいて高速で改善を繰り返すグロースハックが不可欠な手法と言えるでしょう。グロースハックは、データ分析を通じてサービスやプロダクト自体に成長や拡散をする仕組みを組み込み、効率的に成果を最大化することを目指します。
御社のウェブサイトも、このようなグロースハックの考え方を取り入れることで、単なる「コスト」ではなく、成果を出し続ける「資産」へと変革させることが可能です。ウェブ制作工房エル・タジェールは、まさにデータに基づいた戦略的なウェブ制作を得意とし、御社のデジタル成長パートナーとして伴走いたします。
エル・タジェールでは、ウェブ解析士がGoogleアナリティクスなどのツールを駆使して徹底的なアクセス解析を行い、現状の課題を明確化します。そして、データに基づいた根拠のあるページ構成や改善策を立案・実行し、コンバージョン率や売上、問い合わせ数の向上に貢献します。
「作って終わり」ではなく、制作後もアクセス解析に基づいた改善提案を継続的に実施することで、ホームページが成長し続けるようにサポートします。このように、エル・タジェールはグロースハックに必要なデータ分析と継続的な改善のサイクルをウェブサイト制作・運用において実現し、御社のグロースを加速させることが可能です。
データに基づいたウェブサイトで、事業の成長を加速させたいとお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。無料のホームページ制作相談も受け付けております。

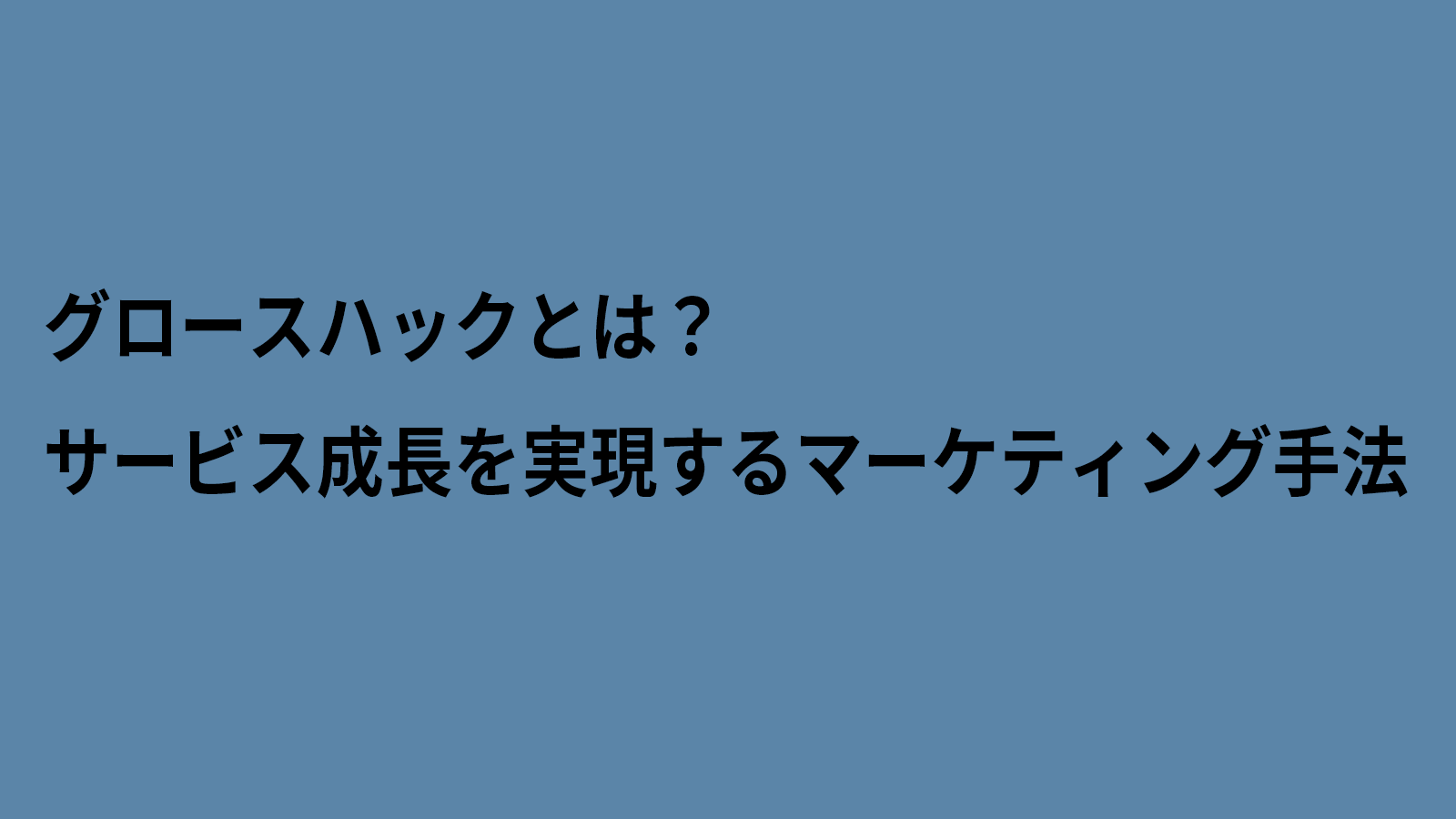



コメントを残す